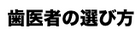日本でも数少ない専門医資格を3つ取得されている森先生。専門性の高い治療はもちろんのこと、よい状態を長期にわたって維持していただけるよう患者さんとのコミュニケーションも大事にされています。そんな先生に医院の特徴や今後についてなどインタビューさせていただきました。

歯学博士
日本補綴歯科学会 専門医 指導医
日本老年歯科医学会 認定医 専門医 指導医
日本歯内療法学会 専門医
先生が歯科医師を志したきっかけは?
私が高校生の頃は、まだ歯科医院の数も少なく、将来性が期待される職業だったので、歯科医師はとても魅力的でした。
また、身内に歯科医師はいなかったのですが、当時の歯科業界では「歯を抜かれた」「削られた」「どんな治療をされているのかわからない」といった話ばかり聞く時代だったので、それなら身内の中で、そういうことに詳しい人がいるのもいいのではと考え、歯科医師を目指すことにしました。
しんご歯科の特徴を教えてください。

大学病院勤務時代は主に入れ歯の研究をしていたので、高齢の患者さんを診る機会が多くありました。その経験から、当院では被せ物や入れ歯といった補綴治療と高齢者の治療を得意としており、私自身、日本補綴歯科学会と日本老年歯科医学会の指導医・専門医資格を取得しています。
また、歯内療法学会の専門医資格も取得しています。歯内療法とはいわゆる「根っこの治療」のことで、補綴分野とは関係がないように思われるかもしれませんが、歯科治療というのはすべてがつながっています。
歯内療法は補綴治療の前段階で行うのですが、根っこの状態によって、しっかり噛めるかどうかの最終的な結果が大きく変わってきます。また、歯を保存する上でもとても重要な分野なので、まず歯内療法で根の治療を行い、補綴治療につなげていく、その流れを専門性を持って治療ができる体制が整っています。
より正確で精密な治療が行えるよう、早いタイミングからマイクロスコープやコンビ―ムCTも導入しています。
当院の目指している入れ歯は、噛める入れ歯ではなくて、安定する入れ歯です。安定する入れ歯とは、噛んだときに痛くない入れ歯です。
まずは入れ歯をできる限り痛くない形に調整し、痛くなくなったら、食べ物を噛み砕くなど「使いこなせる」ようになっていただきます。
保険外の入れ歯であっても、保険の入れ歯であっても、初めての入れ歯はどうしても違和感があって気持ち悪いものです。
なので、最初から保険外の入れ歯を選択するよりも、まずは保険の入れ歯で慣れて、使いこなしていただくことがスタートだと考えています。
使いこなせるようになった上で、内側が薄い金属で作られている違和感の少ない入れ歯や、インプラントを併用した保険外の入れ歯を検討していただければと思います。
患者さんへの説明に力を入れているという歯科医院は多いと思いますが、当院ほど丁寧に行っているところは少ないかもしれません。
現在の歯の状態や治療内容をしっかりと理解していただいた上で、患者さんにもご協力いただかなければよい結果を出したり、よい状態を維持したりすることができません。そのため、当院では保険診療・自費診療に関わらず、当院のスタッフやドクター全員が十分な時間をかけて丁寧に説明を行っています。
また、患者さんの健康状態や口腔内の変化を知るきっかけ作りとして、世間話も大切にしています。プライベートでイベントや予定がある場合は、次回来院時にその話題から会話を始めることもあります。
患者さんも前回の話を覚えてくれているとなると信頼にもつながるので、世間話も交えながら、フレンドリーな対応を心がけています。
大学病院での経験と開業する当院の隣が老健施設だったこともあり、できる限り高齢者の方にとって居心地のいい空間、通いやすい医院をコンセプトに設計しました。
なので、当院は完全バリアフリー設計になっており、診療室内は土足のまま入っていただけます。また、診療室内は狭苦しくないように、広い空間になっているので、車いすでも出入りしやすく、そのまま治療も受けていただくことが可能です。

今後の歯科業界についてと先生の展望を教えてください。
私が歯科医師を目指していた頃は、歯科医院の数はそれほど多くありませんでした。
しかし、その後は急激に増加し、近年ではやや減少傾向にあります。
物価高の影響もあり、現在では保険診療だけでは経営が厳しく、赤字になる医院も少なくないと言われています。
そうした状況の中で、保険診療の流れは予防歯科へとシフトしつつあります。最近話題になっている「国民皆歯科健診」も、歯科健診を通じて疾患を早期に発見し、早期治療につなげることで医療費を抑制しようという取り組みの一環です。
当院は開業して23年になります。これまでは主に根管治療や補綴治療を中心に行ってきましたが、近年は定期健診や予防歯科で通院される患者さんも増えており、時代の流れに合わせてメインテナンスにも力を入れるようになってきています。
こうした保険診療の変化の中で、今後、補綴治療が保険適用外になる可能性もゼロではありません。そのため、スキルの維持や新しい知識・術式の習得がますます重要になると感じています。
仮に自費治療となり費用が高額になったとしても、自信をもって「このような結果を出せます」と言えるように、日々向学心を持って研鑽を重ねています。
今後も勉強会などで若い先生方とともに学びながら、常に新しい知識や技術を身につけていきたいと思います。